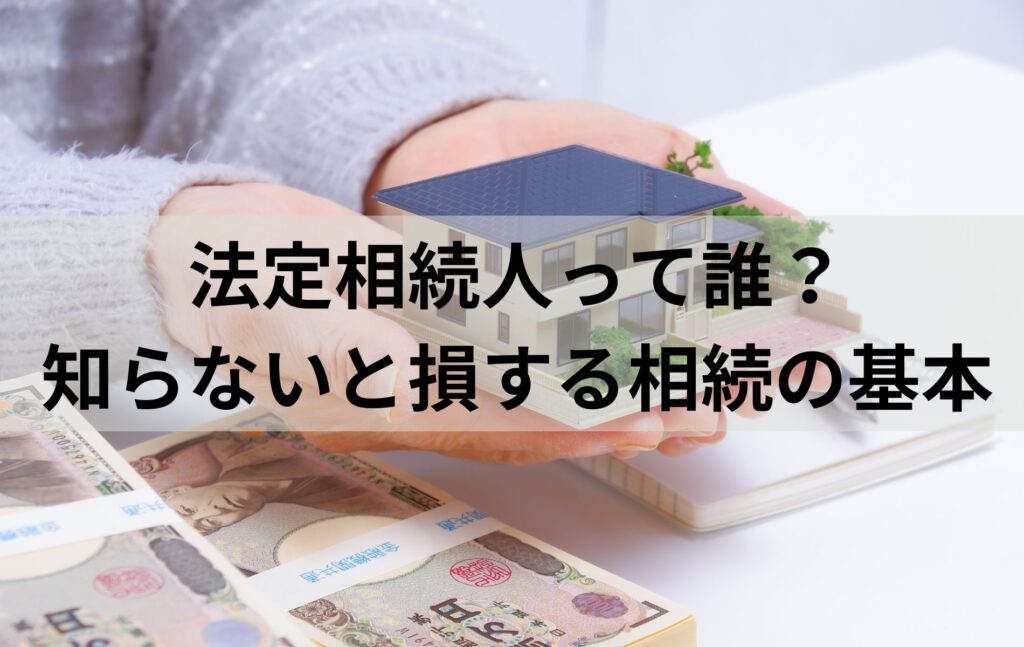遺留分について知っておきたいこと~妻の視点から考えてみる~
この記事では遺留分(いりゅうぶん)について、妻(配偶者)の立場から考えていきたいと思います。妻として「自分の権利はどうなるのか?」と不安を感じる方も多いでしょう。夫に兄弟がいる場合や子どもがいない場合に焦点を当てて解説していきます。
遺留分とは何か?
そもそも、遺留分とはなんでしょうか?遺留分とは、法律で定められた相続権を保障する制度です。相続人は、亡くなった方の書いた遺言書により財産を分配しますが、実際は、全く自分には財産が残されていなかったということもあるはずです。しかし、法定相続人には法律で保障された権利があります。この権利のことを、「遺留分」といいます。「遺留分」制度は、特定の相続人が財産を確保できない事態を防ぐために存在します。
遺留分が認められる相続人
遺留分を請求できる相続人は以下の通りです。
- 配偶者
- 子ども(直系卑属)
- 両親や祖父母(直系尊属)
ポイント
兄弟姉妹には遺留分は認められません。
遺留分の割合
遺留分の割合は法定相続分に基づいて計算されます。
- 配偶者と子どもの場合
→遺産全体の1/2が遺留分となります。 - 直系尊属(親など)の場合
→遺産全体の1/3が遺留分です。
このようにして算定された遺留分を総体的遺留分といいます。単独相続であればこの割合を遺留分を算定するための財産の価額に乗じた金額が遺留分になります。ただ、共同相続の場合は、総体的遺留分に各相続人の法定相続分を乗じて算出します。
ポイント
遺留分を算定するための財産の価額とは
被相続人が相続開始の時において有していた財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額になります(民法1043条1項)
法定相続分については以下の記事をご覧ください。
遺留分侵害額請求とは?
もし夫(配偶者)が遺言書で財産をすべて兄弟に譲ると指定していた場合でも、配偶者として最低限の取り分(遺留分)を確保するため、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。この請求によって、自身が受け取るべき金額を金銭で請求することが可能です。
請求期限(消滅時効)
遺留分侵害額請求には期限があります
- 相続開始および遺留分侵害の事実を知った時から1年
- 相続開始の時から10年
この期限を過ぎると請求権は消滅してしまうため注意が必要です。
子どもがいない夫婦の場合
子供がおらず、亡くなった夫の兄弟がいるケースを考えてみましょう。
被相続人(旦那様):財産総額3,000万円
- 配偶者(妻):法定相続人
- 旦那様の兄弟:法定相続人
例えば、夫は「全財産を兄弟に譲る」と遺言書を残していました。この時、妻であるあなたには以下のような権利があります
- 法定相続分を算出する:3000万円 × 1/2 = 1,500万円
- 法定相続分に遺留分割合を乗じる:1500万円 × 1/2 = 750万円
つまり、あなたは750万円を兄弟に対して請求できる権利があります。
遺留分に関する注意点
生前贈与も対象になる場合がある
被相続人が生前に特定の人物へ財産を贈与していた場合、その贈与財産も遺産総額に含めて計算されることがあります。これは相続人以外のものに対する贈与と相続人に対する贈与とで別に考えます。
相続人以外の場合、相続開始前1年間に贈与したものに限り遺留分として算定されます。一方、相続人に対する贈与は原則相続開始前の10年間について算定されます。
話し合いで解決できないとき
話し合いで解決できない場合には調停や裁判といった法的手段に進むケースもあります。
専門家への相談
遺留分問題は法律や計算方法が複雑です。弁護士や行政書士など専門家への相談がおすすめです。特にトラブルになりそうな場合には早めにアドバイスを受けましょう。
そして、ご自身の遺言書を作成したいと考えている場合にも、将来の遺留分について配慮することが重要です。
公正証書遺言がおすすめ
公正証書遺言は、公証役場で作成されるため、安全性や信頼性が高くおすすめです。また、公証役場で保管されるための紛失や改ざんのリスクもありません。
以下の記事に公正証書遺言のメリット・デメリットを詳しく記載しています。
まとめ
「遺留分」という制度は、一見すると複雑ですが、法定相続人として最低限の権利を守る重要な仕組みです。 特に子どもがいない夫婦の場合や夫に兄弟姉妹がいるケースでは、この制度について正しく理解していると不安やトラブルを防ぐことができます。
ご相談や不安な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
投稿者プロフィール

-
2児の母。
市川で山田弓行政書士事務所を開業。
専門は相遺言関係業務。
最新の投稿
 お知らせ2026年1月6日新年のご挨拶
お知らせ2026年1月6日新年のご挨拶 行政書士関係2025年11月14日知っていますか?行政書士法が改正します
行政書士関係2025年11月14日知っていますか?行政書士法が改正します 相続2025年11月8日ご存じですか?公正証書のデジタル化
相続2025年11月8日ご存じですか?公正証書のデジタル化 お知らせ2025年4月22日建設キャリアアップシステム登録事業者になりました
お知らせ2025年4月22日建設キャリアアップシステム登録事業者になりました